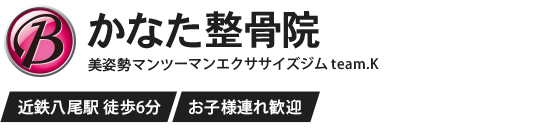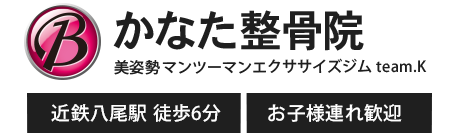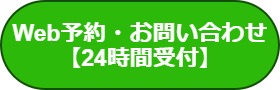10月31日 その【背中の張り】暴飲暴食が原因かも?!

秋は新米、サンマ、栗、サツマイモなど、美味しいものがたくさん!ついつい食が進んでしまう季節ですね。
しかし、最近「背中がいつも張っている」「胃の裏側が重い」「どうも体がダルい」と感じることはありませんか?
その背中の不快な張りは、単なる姿勢の問題ではなく、食べ過ぎや飲み過ぎによる「内臓の疲れ」が原因となっている可能性が高いのです。
今回は、内臓疲労が頑固な背中の張りに変わるメカニズムと、整骨院だからこそできる根本的なケアについて解説します。
1. 食べた分だけ背中が張る!内臓と筋肉の「反射」とは?
私たちの体は、内臓の不調を知らせるために、自律神経を介して筋肉にサインを送る仕組みを持っています。これが「内臓体性反射」です。
これは、自律神経を介して起こる、体内の防御反応の一つです。
内臓体性反射のメカニズム
- 内臓の異常信号: 胃腸の疲労、炎症、機能低下など、内臓に何らかのストレスや問題が発生します。
- 信号の伝達: 内臓の異常を示す信号が、内臓を支配する自律神経を通じて、脊髄(背骨の中を通る神経の束)に伝わります。
- 神経の混線(収束): 脊髄では、内臓から来た信号と、皮膚や筋肉(体性)から来た信号が、同じ神経細胞や経路に集約(収束)して脳へ送られます。
- 反射の発生: 脳が内臓からの信号を、体の表面からの痛みや張りの信号だと誤認したり、脊髄内で信号が交錯したりすることで、実際には問題のない背中や肩の筋肉が反射的に緊張し、痛みやこりとして感じられます。
📌 内臓と背中の意外なつながり
暴飲暴食で胃や腸が疲労すると、その信号が神経を通じて背中の筋肉へと伝わり、反射的に筋肉を硬直させます。
- 特に、胃の裏側やみぞおちの高さにある背中が慢性的に張る場合、胃や肝臓が悲鳴を上げているサインかもしれません。
- 内臓が疲弊し硬くなると、その周りの背骨や肋骨の動きも悪化し、背中全体の血流が停滞。結果的に、マッサージでも取れない頑固な「深部のコリ」へと進行してしまうのです。
📌 姿勢の悪化が内臓疲労を加速
お腹がいっぱいになると、私たちはつい背中を丸める(猫背)姿勢をとりがちです。
この姿勢は、お腹の奥にある内臓を物理的に圧迫し、胃腸の働きをさらに妨げます。また、猫背によって背中側の筋肉が常に引き伸ばされ、背中の張りが一層強くなるという悪循環に陥ります。
2. 胃腸を休ませるためのセルフケアとリセット術
背中の張りを和らげるには、内臓の疲れを取ることが大切です。
- 食べる量を調整する: 腹八分目を意識し、特に夜は胃腸に負担をかけないよう、就寝3時間前までには食事を済ませましょう。
- 体幹を温める: 温かい飲み物や腹巻きなどで、お腹の中心部を温めます。内臓の血流が改善し、機能回復を促します。
- 深呼吸: 食後に背筋を伸ばしてゆっくりと深呼吸を数回繰り返すと、圧迫された胃腸が解放され、副交感神経が優位になりリラックスできます。
3.内臓の疲れを取るストレッチ・運動
内臓そのものを直接ストレッチすることはできませんが、内臓の働きをサポートし、疲労回復を促すために効果的なのは、内臓を圧迫している体の緊張を緩めたり、内臓周りの血流を改善したりするストレッチや運動です。
特に、自律神経を整える呼吸法や、内臓を包む腹腔周りの筋肉を動かすストレッチが推奨されます。
以下に、内臓の疲れを取るのに役立つ簡単なストレッチと運動をご紹介します。
1. 腹式呼吸・逆腹式呼吸 (自律神経を整える)
内臓の働きは自律神経によってコントロールされています。深い呼吸で副交感神経を優位にすることで、内臓の休息と消化・排出機能を高めます。
- 方法: 仰向けに寝るか、楽に座ります。
- 息を吸う時: ゆっくりと鼻から吸いながら、お腹を大きく膨らませます。
- 息を吐く時: 口をすぼめて、細く長く(吸う時間の2倍程度の時間で)吐き切りながら、お腹をへこませます。
- ポイント: 1回5分程度、毎日継続しましょう。
2. 体幹のねじりストレッチ (内臓の血流促進)
内臓周りの筋肉を優しくねじることで、内臓に軽い刺激を与え、血流と動きを促します。
- 方法(仰向け):
- 仰向けに寝て、両膝を立てます。両腕は肩の高さで真横に開きます。
- ゆっくりと息を吐きながら、両膝を揃えたまま、右側に倒します。顔は左に向け、目線は天井に向けます。
- 腰や背中が気持ちよく伸びる位置で、深い呼吸を30秒キープします。
- ゆっくりと中央に戻し、反対側も同様に行います。
3. 股関節を開くストレッチ (骨盤周りの緊張緩和)
骨盤周りや股関節が硬いと、下腹部の血流が悪くなり、腸の働きにも影響します。
- 方法(合せき):
- 床に座り、足の裏と裏を合わせて、膝を外側に開きます。
- 背筋を伸ばし、気持ち良い範囲で上体を前に倒します。
- 股関節の内側が伸びているのを感じながら、30秒キープします。
- ポイント: 痛みを感じない範囲で行いましょう。
4. 軽い腹筋の運動(ドローイン) (内臓の正しい位置へのサポート)
内臓を正しい位置で支えるインナーマッスル(腹横筋)を鍛えることで、内臓への負担を減らします。
- 方法: 仰向けに寝て、膝を立てます。
- 息をゆっくりと吐きながら、おへそを背中の方へ引き寄せるように、お腹をへこませます。
- お腹をへこませたまま、浅い呼吸を10秒間キープします。
- ゆっくりと力を緩めます。
- ポイント: 腹筋運動ではなく、お腹を薄くすることを意識しましょう。
実施のベストタイミング
- 食後すぐは避ける: 食後1〜2時間程度空けてから行いましょう。
- 入浴後や就寝前: 体が温まり、副交感神経が優位になりやすい時間帯が最も効果的です。
4. 整骨院で「内臓疲労」による背中の張りを根本改善!
当院では、内臓の疲労からくる背中の張りに対し、以下の専門的なアプローチを行います。
セルフケアや休息だけでは背中の張りが取れない場合、すでに背骨や肋骨の動きがロックされているサインです。内臓の専門家ではない整骨院ですが、体性反射による筋骨格系の不調を改善するのは得意分野です。
- 肋骨と背骨の動きの調整: 内臓の動きと密接に関わる背骨・肋骨の関節を調整し、内臓への圧迫やストレスを軽減。内臓が正常な位置と環境で機能しやすい状態を作ります。
- 深部の筋膜リリース: 長期間の疲労で硬直した背中の深層筋や筋膜(ファシア)に対し、集中的な手技でアプローチ。血流を劇的に改善し、頑固な張りを解消します。
- 姿勢指導と矯正: 内臓を圧迫しない正しい姿勢(骨盤と背骨のバランス)を指導・矯正し、内臓が働きやすい環境を維持できるようにサポートします。
整骨院で重要視される理由
整骨院や治療院では、マッサージや姿勢矯正だけでは改善しない慢性的な痛みやこりの原因として、内臓体性反射を考慮することがあります。
- 例: 頑固な肩こりが、実は右側の肝臓の疲労による反射であるケース。または、みぞおちの裏側の背中の張りが胃腸の疲労からきているケースなどがあります。
この反射によって引き起こされた痛みの場合、内臓の疲労回復(食生活、休息)と、反射によって硬くなった関連筋肉の緊張を緩めるアプローチを組み合わせることが、根本的な改善に繋がると考えられています。
「揉んでも治らない」「いつまでも続く背中の張り」には、単なる筋肉の問題ではない、内臓からのSOSが隠れているかもしれません。
辛い症状を「年のせい」「疲れのせい」と諦めてしまう前に、一度、当院にご相談ください。
当院では、姿勢や筋肉の歪みを整えるだけでなく、内臓との関連性も考慮に入れながら、体全体のバランスを見て根本的な不調の改善を目指します。
「食欲の秋」を楽しむためにも、「背中の張り」という体からのサインを無視しないでください。内臓と体の両面を整えて、年末を元気に迎えましょう!
八尾市、柏原市で肩こり、腰痛でお困りの方はかなた整骨院へ(^^)/
八尾市かなた整骨院 https://instagram.com/kanataseikotsuin?igshid=ZjE2NGZiNDQ=